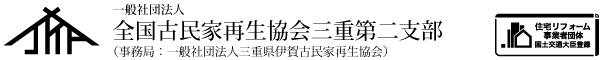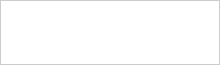古民家再生協会の小野寺です。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
↑この写真は「制震ダンパー」というものです。
柱と柱の間に入れる制震装置で、古民家の耐震には欠かせないものです。
「制震」とは、建物の一部にわざと揺れる部分を設け自身の揺れを吸収するものです。
真ん中の黒い筒状のところにオイルが入っており、これは自動車用ショックアブソーバ(:自動車の中の機械的な衝撃を吸収する装置のこと)の量産技術を応用したものだといいます。
さてなぜ「耐震」ではなく「免震」を行うのでしょうか?
それは古民家の造りに関係しているからです。
古民家の多くは伝統構法で建てられています。
伝統構法とは、柱と横架材(※梁・桁(けた)・貫(ぬき)などの水平方向に渡された部材)からなる垂直と水平の直線材で構造をつくる構法のことで、土壁や貫と板壁などを入れて全体を固めています。
地震が発生すると揺れて地震力を逃がす減衰力のある「免震(めんしん)」と建物にかかる振動を吸収する「制震(せいしん)」の中間の性質を持っています。
このようなことから、変形をできるだけ抑えるように地震の揺れに耐えるように設計された「耐震」とは違い、地震のエネルギーを吸収しようと設計された「制震」が古民家には適しているのです。
建物の大きさによって入れる数量は様々ですが、今回のお家ではこの制震ダンパーを6ヵ所入れました!
建物を支えるためにリフォームにおいて、耐震補強は重要なポイントになってきます。
在来工法の建物とは違った伝統構法での耐震補強を行っていきますが、古民家でも耐震補強を行えるということを今回わかってもらえたら嬉しいです。
これからもリフォームは完成に向けて進んでいきます。
進捗を楽しみにしていてくださいね!