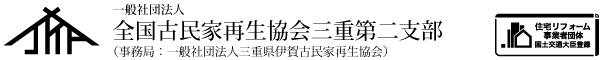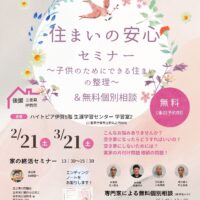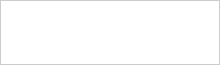古民家再生協会の小野寺です。
雪が降って寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて今回は「金輪継ぎ」についてご紹介します!
「金輪継ぎ」に関しては、過去のブログでも一度触れていますのでそちらもぜひお読みくださいね。
その時のブログはこちらから→伝統的な継ぎ手「金輪継ぎ」
リフォームしようと家を解体し終わったら、写真のようにシロアリに柱の根元が食われていたことはありませんか?
上の写真の柱は表に見えていたわけではありませんが、壁をめくって解体を行ったらこのような状態になっていました。
リフォーム後もこの位置に柱を設ける場合、この柱はすべてを新しくしないといけないのでしょうか?
実はそういうわけでもありません。
そこで使われている技法が「金輪継ぎ」です。
↑After
分かりづらいかと思いますが、この写真は下の写真の一番右の柱の根継ぎ写真です。
真ん中に杭のようなものがあり、これを押し切って完成です。
簡単には取れない造りになっています。
この現場では合計6本の金輪継ぎを行いました。
写真でわかるように柱継ぎを行っている高さはバラバラです。
このように柱の「腐っている部分」のみを切り取り柱を継ぐので、これまで通り残すことのできる部分はそのまま利用できます。
「金輪継ぎ」とは、伝統的な柱の継ぎ方で柱の腐っている部分だけを切り取り、その部分を新しい木材で継ぐことです。
継手の中でも接合部がしっかり噛み合う構造になっているので、強度が非常に高いものになっています。
また、釘やボルトを一切使わず柱を継ぐので、見た目も美しく古民家や寺院などの伝統的な木造建築で使われます。
ただ構造が複雑で機械では作ることができず、すべて大工さんが手作業で行っています。
金輪継ぎは日本の大工さんの伝統的な技法であり、その強度や美しさは現代にも受け継がれています。
それでもこれができる大工さんは年々減ってきているようですので、伝統的な大工技術に興味のある方は、ぜひ深く学んでみてはいかがでしょうか?